難病と生活保護支援
2025/3/11 公開
生活保護制度は、日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められた生存権に基づく制度です。条文の通りすべての国民の権利であり、難病であっても除外されることはありません。
この記事では、指定難病の患者が生活保護適用となった場合にどのような支援が受けられるのか、制度の説明を踏まえてご紹介します。
生活扶助(生活費)
生活保護の基本となる支援です。収入や資産が基準を下回る場合に、生活費として一定額が支給されます。指定難病患者の場合、病気により仕事ができないことや、生活のために必要な支出が増加することが考慮され、生活扶助が支給されます。
医療扶助
生活保護を受けている人は、医療費の支給ではなく「医療サービスの支給」が行われ、自己負担が無料となります。診察代や検査代、薬代などにおいて適用され、指定難病医療費助成制度の有無に関わらず基本的に窓口での支払いは発生しません。ただし入院時の個室代やアメニティなど、実費となる項目には費用負担が発生するため注意が必要です。
受診のための通院費などは、移動方法によって扶助が受けられない可能性があるため、事前に担当のケースワーカーへ相談が重要となります。
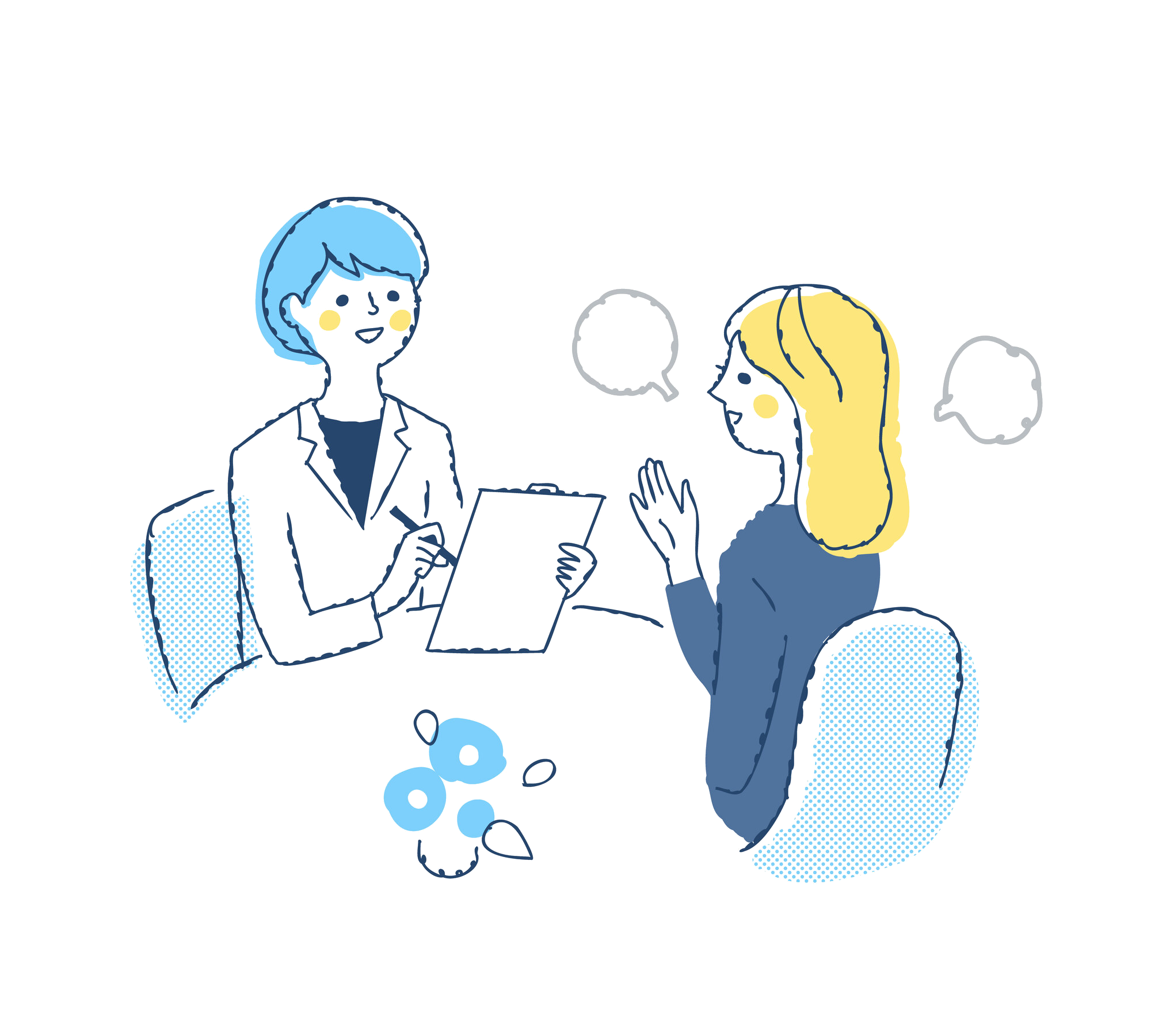
住宅扶助
生活保護を受ける場合、住んでいる場所によって住宅扶助が支給されます。家賃などの住宅費用のうち、定められた基準に応じた費用の支給が行われます。自治体によって基準額が変わるため、転居の際などはケースワーカーと相談しておくことが必要です。また、転居にかかる費用は状況や条件によって支給されない場合もあります。
教育扶助
子どもがいる場合、教育扶助が支給されます。子どもが学校に通っている場合、必要な教育費用(学用品や学校行事の費用など)が支給され、病気を抱えた家庭でも教育に対する支援が受けられます。
就労支援
生活保護制度は自立に向けた支援制度であり、就労支援もその一環です。ケースワーカーが公共職業安定所と連携し、就労へのサポートを行います。
介護扶助
介護認定を受けている場合、介護サービスは医療サービスと同じく現物支給が行われ、自己負担なく利用ができます。病状の進行により介助が必要となった場合でも、安心して支援が受けられます。

生活保護を受けるためには、必要な書類や証明書を提出して審査を受ける必要があります。難病の有無だけで審査が通りやすくなることはありませんが、症状による生活のしづらさ・社会活動への参加しづらさがある場合、支援を受けることでよりよい生活が送れるようになる可能性があります。まずは各自治体の福祉事務所に相談してみることをお勧めします。

