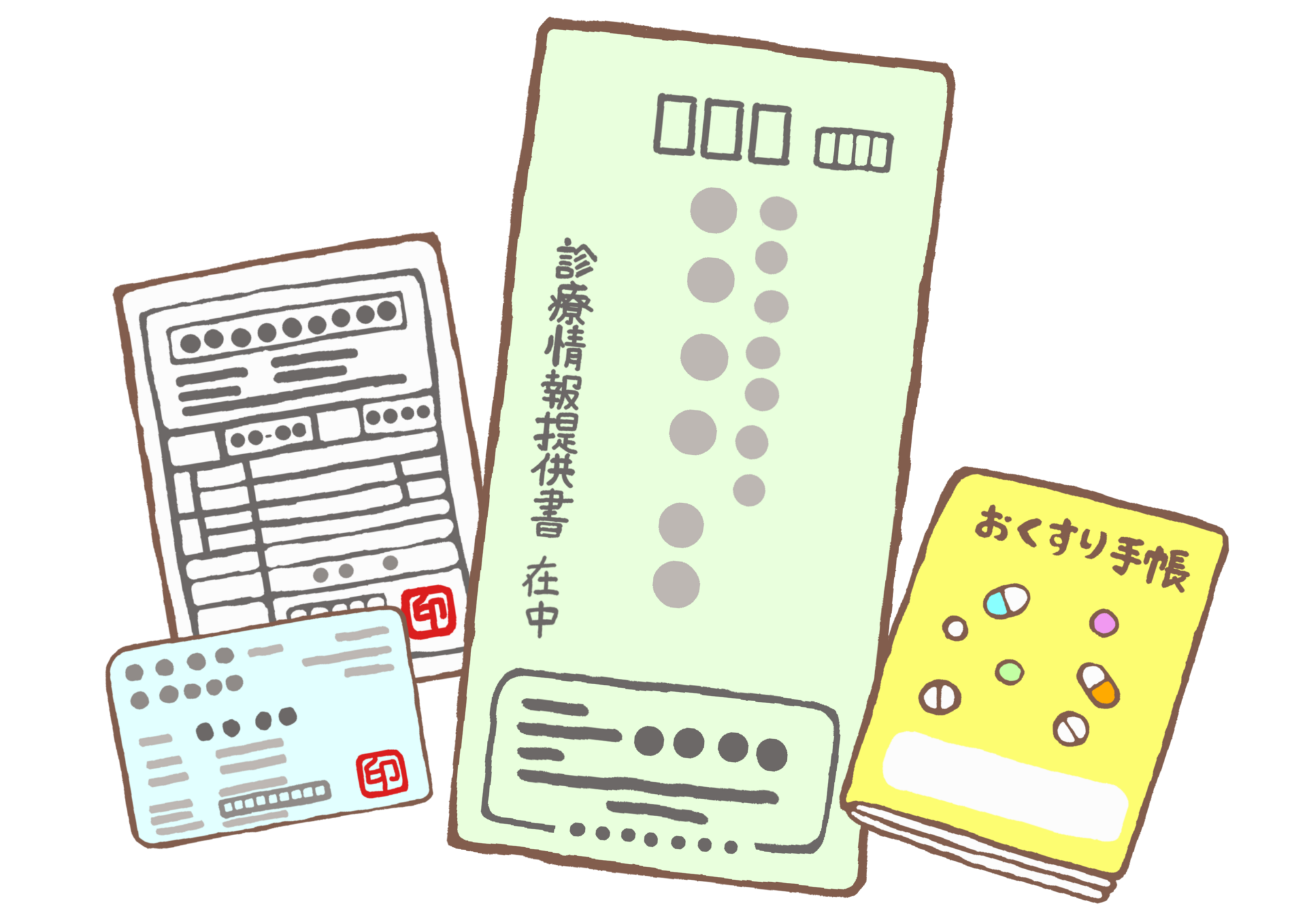難病の医療費の申請方法
2025/3/10 公開
医学が進歩した現代においても、原因や治療法が分かっていない病気が数多く存在します。
その中でも患者数が少なく、長期の療養が必要な病気を「難病」と呼びます。継続した治療を必要とし、かつ診断基準が確立したものとして厚生労働省が認めた難病が「指定難病」です。
令和6年4月1日の時点で、指定難病の数は341疾患に上ります。
難病の治療にはさまざまな検査を定期的に受ける必要があるものや、高価な薬を使用することも少なくありません。治療期間が長期に及ぶため、医療費の負担が大きくなると治療の継続も難しくなります。
そのため、指定難病の治療にかかる医療費の自己負担分について、公費での負担を行う制度が指定難病医療費助成制度です。
指定難病医療費助成制度を受けるための申請方法は、住んでいる地域によって異なる場合がありますが、一般的な流れは以下の通りです。

医師の診断を受ける
指定難病であることを証明するために、まず医師による診断を受ける必要があります。医師であればだれでも診断をつけられるということではなく、都道府県知事や指定都市市長による指定を受けた医師である必要があります。診断後、医師により臨床調査個人票と呼ばれる診断書が作成されます。
指定難病医療費助成制度の申請
次に必要となる手続きが、医療費助成制度の申請です。申請先は、住民票がある市区町村の役所や福祉課、保健所などで行います。申請に必要な書類としては申請書と臨床調査個人票のほか、本人確認書類や健康保険証のコピー、所得確認書類などがあります。
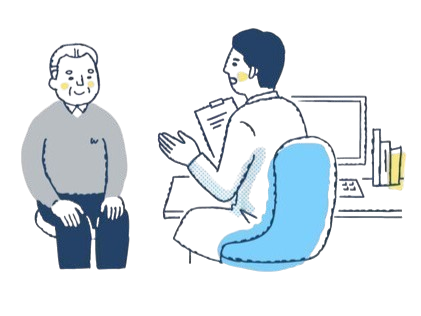
医療受給者証の交付
申請書類の提出後、基準を満たしているかどうか書面での審査が行われます。審査が通ると、指定難病患者として認定され、医療受給者証および自己負担額上限管理票が交付されます。
認定後は、指定難病に対する医療費の自己負担額が軽減されます。受診時に医療機関での支払い時に医療受給者証と管理票を提出することで、負担割合の軽減や、認定された上限額の適用が行われます。ただし、助成が受けられるのは指定難病に関する治療にかかる費用のみとなることに注意が必要です。
申請に必要な手続きや書類については、住んでいる自治体や保健所に確認すると良いでしょう。
参考:難病情報センター(https://www.nanbyou.or.jp/)